top of page
検索


早食い卒業!咀嚼という食べ過ぎ防止術
「もう5回だけ多く噛む」。たったそれだけで、食べるスピードや満腹感、食後のだるさまで変わります。ここでは噛むこと(咀嚼)が体に起こす変化をやさしく解説し、和食のスタイルを使って無理なく実践する方法までまとめました。🍵🥢
-


鍛えると回復はセット‼️ "分子シャペロン"で筋肉と神経をリカバリー
運動で筋肉を酷使すると、当然筋繊維は傷つきます。しかし、見落とされがちなのが神経系の疲労。
筋肉を動かすには、脳からの命令がスムーズに伝わることが必要です。この"神経の伝達"にもストレスがかかり、リカバリーを必要とするのです。そこで鍵となるのが、「分子シャペロン(molecular chaperones)」。ヒートショックプロテイン(HSP)やコールドショックプロテイン(CSP)といった分子シャペロンは、細胞レベルであなたの体を守り、回復を促してくれる頼もしい存在です。
-


筋トレとプリン体の意外な関係──内因性代謝、進化、栄養戦略まで徹底解説!
「プリン体=ビールや肉」と思われがちですが、実際にはそれは“氷山の一角”にすぎません。私たちの体は、日々の細胞代謝のなかで膨大な量の“内因性プリン体”を生み出しています。特にハードな筋トレを継続する方にとって、この内因性の代謝過程とどう向き合うかは、見落とされがちな健康管理の鍵です。さらに、私たち人間は進化の過程で、体内でアスコルビン酸(ビタミンC)を合成する能力や、尿酸を分解する酵素(ウリカーゼ)を失ってきました。これらは単なる欠損ではなく、生理機能や酸化ストレスとのバランスに深く関わっています。この記事では、フィットネス愛好家の皆さんに向けて、内因性プリン体の基礎から筋トレとの関係、そして進化的背景に基づいた栄養管理まで、一次ソースに基づき丁寧に解説します。
-


【吸収率だけでは不十分?】筋肉をつけたい人がまず知るべき「たんぱく質代謝」の真実
最近、「吸収しないと意味がない」と謳うプロテインや高機能たんぱく質食品をよく見かけるようになりました。たしかに、消化吸収されなければ筋肉にはなりません。吸収率が高いということは、それだけアミノ酸として体内に取り込まれる量が多い、という意味であり、重要な要素のひとつです。...
-


地産地消は本当に健康にいいの?耳あたりの良い言葉に潜む思い込みと正しい見方
「地元の野菜は新鮮で安心」「天然由来はカラダにやさしい」——そんな耳あたりの良い言葉に惹かれて商品を選んでいませんか?地産地消や自然食品は地域活性や食文化に貢献する一方で、「本当に健康にいいのか?」という視点では冷静な検討も必要です。本記事では、地産地消と健康の関係性を科学的に紐解きながら、天然 vs 人工、そしてバイアスに基づく判断の落とし穴についても詳しく解説します。
-


加齢ではなく“老化”を止める。テロメアと筋トレの正しい関係
筋トレは、筋肉だけでなく“細胞の若さ”にも影響を与える――。これは近年の分子生物学的研究で明らかになってきた事実です。老化の指標の一つとされる「テロメア」は、細胞分裂のたびに短くなる構造。激しすぎる運動はこのテロメアを加速的に短縮させる一方、適度な運動はそれを保護することがわかっています。本記事では、テロメアの視点から見た“老けない筋トレのやり方”を、科学的根拠とともに解説します。
-


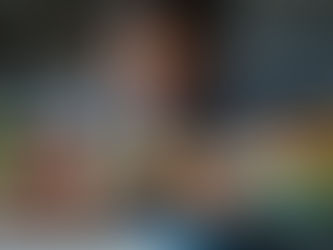

健康志向が逆に不健康に?オルトレキシアの症状・原因・対応方法
「健康的な食事が逆にあなたを苦しめていませんか?」過度な健康志向が招くオルトレキシアについて解説。症状、原因、そして「健康」と「不健康」の境界線を見つけるヒントを提供します。食事で不安を感じる方は必読。
-


代表パーソナルトレーナー・平木翔のプロフィール
はじめまして。『ふぃっとねす工房』代表の平木 翔(ひらき しょう)です。 尼崎市を拠点に、パーソナルトレーナー・講師として20年以上、地元の皆様の健康と目標達成をサポートしてきました。このページでは、私の経歴や資格、ボディビル競技での活動、そしてトレーナーとしての想いについてご紹介します。
-
bottom of page



